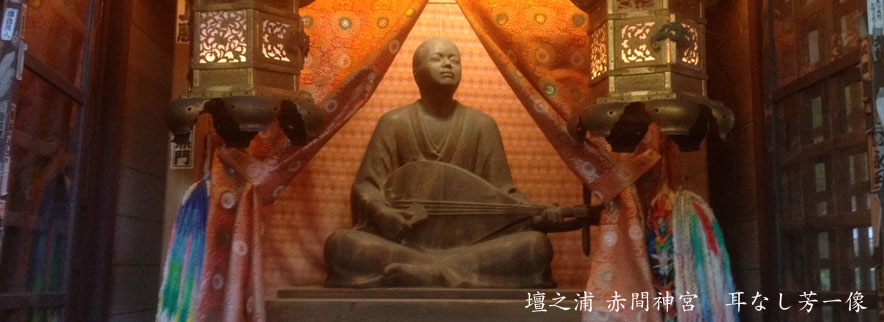天覧の栄誉
超えて十三日またまた北白川宮殿下の御召しを蒙り、六月十八日には麻布御川邸に参殿し富美宮、泰宮両内親王の御前に小督、楠公、扇の的等を弾奏し、二十一日に再び北白川宮殿下御お召しにより石童丸、湖水渡、扇の的等を演奏した。明治四十年五月六日には高輪の御用邸に参内して常宮、周宮両内親王の御前に経正、石童丸、湖水渡を弾奏し、翌四十一年一月二十一日には小田原御用邸に再び両内親王の御召しを戴き伏見の吹雪、四條綴、義士の本懐、師長等を演奏し、四月二日三度御召しを蒙り粟津原、錦の御旗、蓬莱山、大塔宮等数曲を演奏した。 Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報