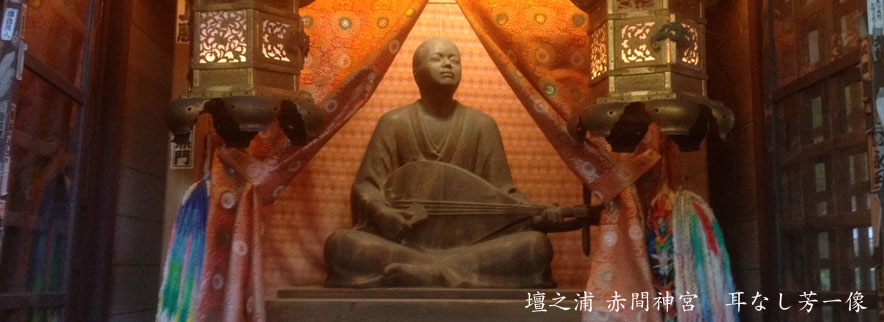「丸くとも一角あれや人心」という古人の句があるが、なかなか味のある言葉だ。今これを弾奏のほうへ移して考えてみるとはなはだ得るところがある。弾奏はギスギスした角ばかりのものは上出来でない。さりとてなだらかな一方で少しも角のないのもまた不出来である。
Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報