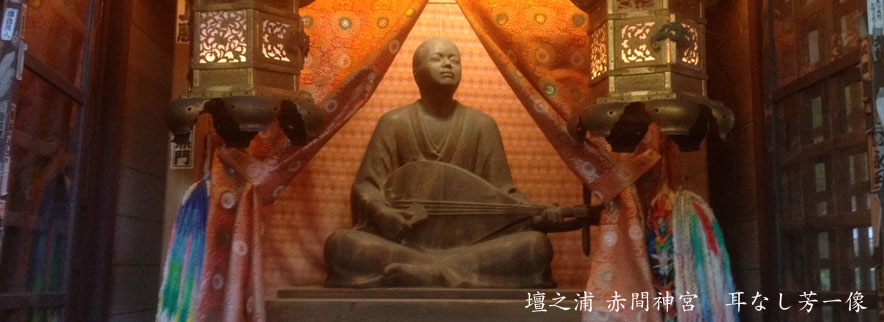くすぐったいお世辞以外、誰だって褒められて悪い気のする者はあるまい。褒められて喜ぶということは人間の持ち前の情であるが、これが弱みとも言える。そこで多くの人から沢山の拍手が起これば嬉しくなるのも否めないだろう。 Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報