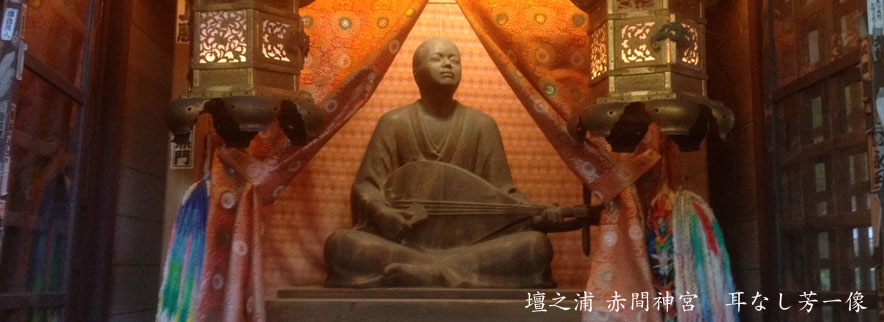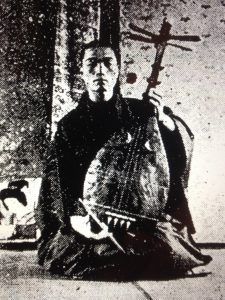弾法練習の時の心得
弾法を練習する際には、必ず前後に歌があると観念して練習すべきである。例えば「切り」の手を練習する場合は前の歌の文句を受けて、また直ぐ後ろへ「大干」の節が来ることを観念して練習するのである。
更にもっと仔細に考えて、広瀬中佐なら広瀬中佐、その他何でもよろしい、とにかくある種の曲を演奏していると観念して弾法の練習をすると好結果を得られる。常にこの気分を忘れてはいけない。決して弾法は弾法として独立したものの如く観念して練習してはいけない。 Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報