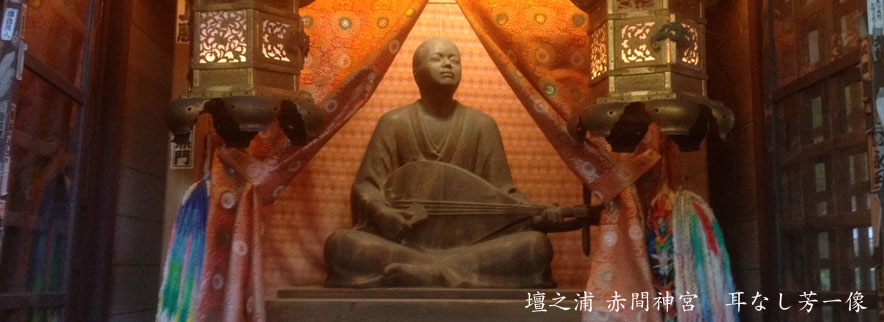音階と余韻
いかに「間」が大切であると言っても「手かず」のない所に「間」はあり得ないのだから「間」を覚えるには「手かず」はもちろん覚えるに決まっているが、さて、「手かず」と「間」とを覚え込んだら次には「音階」に充分な注意を払わねばならない。 Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報