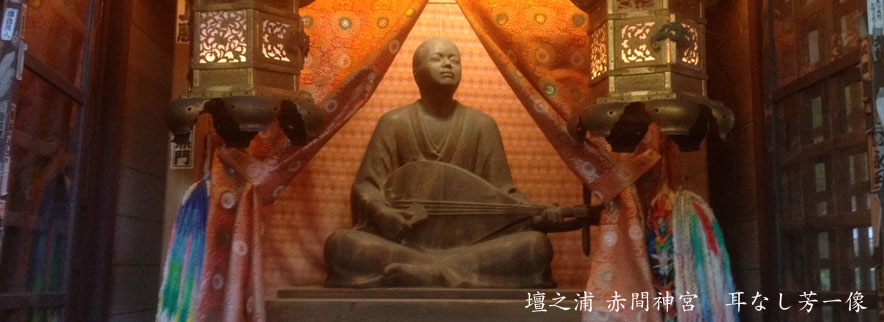ここは本所の吾妻橋。大正四年の川開きの夕暮れ、近くに住む中村夫婦は幼い子供を祖母に預け、残る年上の兄弟姉妹を引き連れて両国の花火見物に出かけた。
道ゆく数多の見物客、雑踏にのまれて歩く隅田の川端はさても黒山の人集り。見渡す限り川を埋め尽くす屋形舟で水面も見えないくらいである。
四女の冨美は今年数えで四つ。生まれて直ぐに先帝陛下がお隠れになったので今日は喪が明けて初めて観る花火大会、冨美は母の浴衣の袖をぎゅっと掴んだまま時折空を見上げては黙って頷いていた。 Continue reading
-
固定ページ
-
カテゴリー
-
リンク
-
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年8月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2013年9月
- 2010年6月
- 1999年1月
-
メタ情報